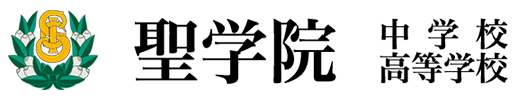イエス・キリストの世界観(3月3日全校礼拝にて)
新約聖書マタイによる福音書 22章15~22節
異邦人と関係を持つこと。
律法で禁じられている。
他方、異邦人と関係を持たないことはローマ帝国を否定すること。
それは反社会的行為。
ファリサイ派の人々がイエスに尋ねる。
「帝国に税金を納めることは正しいことか?」と。
どちらを肯定してもユダヤ文化を否定するか、社会制度を否定するかになる問いかけ。
イエスを糾弾するには十分な証拠を得ることになる。
これに対してイエスは流通している硬貨を持って来させ
「皇帝のものは皇帝に」「神のものは神に」と答える。
ファリサイ派の問いかけを回避する。
イエスは機転が利くが、この物語のテーマではない。
ファリサイ派とイエスの違い。
それを先鋭化することにこの物語のテーマがある。
ファリサイ派とイエスの違い。
それは何か。
結論を言うならば「世界観が違う」
ならば、その世界観とは何か。
I am who I am
神が自らを表した時に語った言葉。
私は私。
私たちは自己確認をする時、
他者に自己を紹介する時、
私でないもので自分を表す。
職業、出身校、地位、年収
自分でないものを私として確認、紹介する。
私でないものに自分を預ける。
私がなくなる。
神が私に預けてくれた私の賜物
それを何故、捨てるのか。
私が私でいたい
私は私でどうやったらなれるのか。
もし私たちがそれを望んだとしても、私たちは自分を表している自分以外のもの
それを捨てることができない。
愛するもの、信頼を寄せているもの
その者に期待をされている。
その者が私を見ている。
その者の言葉、その者の期待を自分に貼り付ける。
自分でなくなる。
愛するものに反発をする。
その言葉に反抗をする。
それで自分を取り戻せるわけではない。
反抗、反発、相手がいる。
自分以外のもの、相手を意識している。
自分がなくなっている。
どうすれば、他者の言葉に支配されずにすむのか。
迎合でも反発でもないところに心を置く。
どちらでも良い。
パウロが晩年に見つけた心の定め方。
税金を帝国に納めるのは律法に適っているのか、いないのか。
ファリサイ派がイエスに詰め寄る。
皇帝のものは皇帝に、神のものは神に。
イエスの答え。
その答えを聞いた私たち
次の行動が定めるか
手元にある硬貨を私はどうすれば良いのか明確になったか。
イエスはファリサイ派への回答はしたかもしれないが、実際にどうすれば良いのか、
その指示をしていない。
私たちがそう考えるのなら、私たちもファリサイ派も同じ世界観。
イエスの世界観と私たちは何が違うのか。
税金を異邦人に払うのは律法にかなっているのか?
自分の手元にある硬貨は結局どうすればいいのか?
なぜこの問いが生まれるのか。
答えが一つだと思っているから。
ここにある世界観
答えはひとつ
真実はひとつ
真理はひとつ
そう思っているから分からなくなる。
皇帝のものは皇帝に、神のものは神に
答えはひとつではない。
敵でも味方でもどちらでも良い。
生きること、死ぬこと、どちらでも良い。
パウロが導き出した心の定め方。
答えはひとつではない。
社会の言葉は知っている。
答えはひとつ。
それを獲得しろ。
それを得ないと幸せにはなれない。
自分を自分でない立派な言葉で表せ。
ひとつの答えを目指して、その頂が他者にも伝わるような立派な言葉で自分を着飾れ。
そう語る社会の言葉は知っている。
それを承知で
そういう言葉が社会の言葉だから聖学院は120年前創立した。
答えはひとつ。
それで平和が実現できたか
それで人は幸せになったのか
答えはひとつではない。
どこにでも答えはある。
どこから行っても必ず行くべきところに行ける。
この世界は神が造った良い世界。
ひとつに固執すること
それはこの世界を信じていない。
Only Oneを見つける
聖人になる
本当の自分になる。
平和、幸福
人が実現しなければならないもの。
聖学院が目指しているもの。
120年間守ってきたもの。