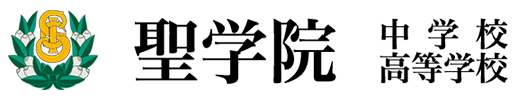普遍を生きるもの(1月22日全校礼拝にて)
新約聖書使徒言行録9章32~43節
聖書を読みました。
聖書は答えが書いてある書物ではありません。
もちろん、なんの答えもないものではないです。
答えへの入り口があるだけです。
ここに記されている文字をただ追っかけて、それを覚えても聖書を読んだことにはなりません。
思考停止にして読むものではなく、この物語は、この言葉は、私たち読者に何を語りかけているのか。
何を考えさせようとしているのか。
聖書は「問い」です。
思考しながら読む。
それが聖書です。
これに私たちなりに、答えていく、それが聖書が望んでいる読み方です。
今日、読んだ物語は私たちに何を問うているのか。
中風という病気の故に八年間、床に伏している者がいる。
亡くなってしまった者がいる。
このどちらもに対してもペテロが癒す、生き返らせるということをします。
奇跡物語と言われるものです。
ここから何を読み取れば良いのか。
床に伏している。
亡くなっている。
この両者に共通しているものはなんでしょうか。
単純化して言うならば、止まっているということでしょう。
止まるは物理的なことです。
ここに心情、感情的なものも加味してみましょう。
床に伏している止まっている者。
この者の心情、何を自分の人生に感じているのか。
亡くなった女性。
この者の感情は亡くなっているのですから推察することはかなわないでしょう。
ただ、この周囲にいた者たちの感情については聖書にも記されています。
床に伏しているもの。
亡くなった者の周囲にいるもの。
この者たちの感情。
悲しい、寂しい、
そういったものでしょう。
もう一歩、考えます。
そこにある感情については「悲しい」「寂しい」でしょう。
では、ここに「ないもの」はなんでしょうか。
この状況で失ってしまったものはなんでしょうか。
「悲しい」「寂しい」に閉じ込められてしまっている原因。
それは「希望」がないということでしょう。
希望がない。
世界が止まります。
病気、死者、
世界が止まっているの象徴です。
聖書が問うていること。
止まっている世界はどうしたらもう一度、動き始めるのか。
物語ではこうなっています。
ペテロが「イエス・キリストがあなたを癒す」そうすると病が癒されたと。
ペテロにとってのイエス・キリストとはなんでしょうか。
今ここにいない方です。
かつていた方です。
また来ると約束をされた方です。
過去と未来にはいる
それは今いないはずのものです。
ところがペテロはイエスは今ここにいるとしている。
いないのにいる。
ないのにある。
「いる」「ある」は時間と空間の座標軸の中で決定されるものです。
いないのにいる。
それは時間と空間の座標軸に縛られていないということです。
時空に縛られていない。
それは普遍ということです。
正義
場所が変われば、変わってしまう。
日本では正義だが、他の国に行ったら正義ではなくなる。
それは正義ではありません。
場所が変わっても変わらないもの
それが正義でしょう。
愛
この人は愛するが、あの人は敵だ。
相手が変われば変わってしまうもの。
それも愛ではありません。
何があっても変わらないもの
それが愛でしょう。
ペテロが止まっている世界に提示したもの。
普遍がある、です。
「止まる」は時間と空間の中に閉じ込められることです。
世界は時間と空間がすべてではない。
変わらないものがある。
普遍がある。
この「普遍」を取り扱うペテロですが、
物語は更に私たちに問いかけていることがあります。
使徒言行録でペテロは三回、癒しをしています。
「イエス・キリストの名によって立て」
「イエス・キリストがあなたを癒す」
イエス・キリストの名前を使っています。
それが三回目
「立て」
とだけ言います。
イエスの名前は登場しません。
物語は何を読者に語っているのか。
ペテロがイエスの名前を語っている時
それはイエスがペテロにとっては指し示すもの
自分とは違うもの
外のものだったのでしょう。
それがイエスの名前を語らなくなった。
ペテロはイエスを自分の中に入れた。
自分とイエスが一つになる。
イエスを生きる。
普遍は
正義、愛、真理
それらは、あそこにありますよ、と案内をするだけのものではありません。
自分のものにすることです。
正義を生きる。
愛を生きる。
真理を生きる。
その時、病の者は癒され、死者は甦る。
世界は動き出します。
希望が始まります。
普遍を生きるもの
それが聖人です。
聖学院が目指す人の姿です。
本当の自分
Only Oneを探す。
それは自らの中に宿っている普遍と出会うことです。
世界を動かす。
そのための準備としての一日を過ごしてください。